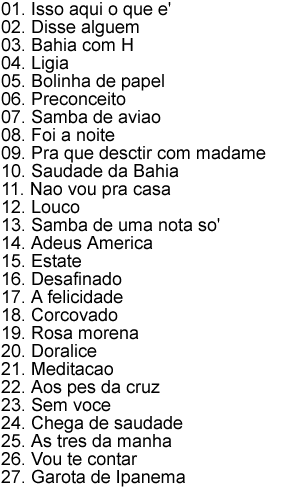2003年9月16日。東京国際フォーラムAホール。午後7時。
アナウンスが流れた。
「開演時刻となりましたが、アーティストがまだ到着していません。開演が遅れることをお詫びします」
笑い声と拍手が起こる。
午後7時15分。
「アーティストはただ今、こちらに向かっております」
再び笑い声と拍手。
午後7時半。
「アーティストが到着しました。準備をしますので、しばらくお待ちください」
またしても拍手と笑い声。他のアーティストのコンサートだったら、暴動が起きているところだが、場内はなごやかな雰囲気に包まれている。
少々暑いのはエアコンを停めているせいだ。これだって他の場合だったらクレームが殺到するに違いないが、誰もがごくあたりまえのこととして受け入れている。
開演が遅れることもエアコンを切ることも、ジョアン・ジルベルトのファンにとっては常識なのである。ジョアンの来日公演は今回が初めてだ。にもかかわらず、やはり常識なのである。ジョアンのファンはジョアンが何を求めているのかをよく知っている。そして、何を与えてくれるのかも。
午後8時。1ベルが鳴り、ロビーでお喋りをしていた人たちも席に着いた。
ステージ中央がスポットライトで照らされている。木の椅子、テーブル、右足を載せる台(ギター用のものではなく、普通の踏み台のようなものを使っていた)、ギターとヴォーカルのマイクをセットしたスタンド、ギタースタンドが並んでいる。
テーブルには水のボトル、コップ、それに円形の時計(目ざまし時計)が置いてある。
午後8時5分。2ベルが鳴った。拍手の後、5000人の聴衆が息をひそめてジョアンがステージにあらわれるのをじっと待つ。
静寂の時間が流れる。クラシックのコンサートでも、こんなに長い沈黙の時間は経験したことがない。5000人の沈黙というのは、それはそれでなかなか迫力があるものだ。
午後8時10分。ギターを片手にジョアンがステージに登場した。大変な拍手を受けて、ジョアンは軽くお辞儀をした。
グレー系のスーツ(ジョアンはレコーディングのときもちゃんとスーツを着るのだそうだ)にブルーのシャツ、銀色の小さな模様が入った濃紺のネクタイ、黒い革靴という服装。髪が薄く、眼鏡をかけていて、ちょっと前かがみになって歩く。風采の上がらない銀行員といった印象を受けるが、目の肥えた人なら、スーツとシャツの仕立てのよさに気がつくはずだ。
ジョアンが椅子に坐り、ギターを弾く構えに入ると拍手がピタッと止む。
「こんばんは」
ボソリと呟いた。
実はそれからのことをあまり憶えていない。いや、正確に記すならば、映像としてではなく、ジョアンの声とギターだけが残っている。
心のどこかに「その姿を見るだけでいい」という思いがあった。72歳という年齢を考えれば当然だ。サラッと45分くらい歌ってステージを降りても、それはそれで仕方がないとも思っていた。
そんなふうに思っていた自分が今は恥ずかしい。歌えなくなったり、ギターを弾く指の動きが鈍くなったら、ジョアンはステージには上がらない。そういう人だ。だからこそ、深い感動を与えることができるのだ。
曲のあいだにお喋りはいっさいなく、淡々と曲を歌いつないだ。テンポの速い曲のときに左膝を大きく揺らす以外は、歌っているときも曲のあいだでもずっと同じ姿勢を崩さなかった。途中、二度ほど喉を指差して何か言ったが。僕はポルトガル語がわからない。喉の調子が悪いと訴えたのかもしれないが、深い声の響きはCDで聴き慣れたそれだった。
いや、正確に記すと、生で聴くジョアンはCDで聴くそれ以上だった。
まず驚いたのはダイナミックレンジがとても広いことだ。ボサノヴァは淡々と一本調子で演奏されるものと思われがちだが、ジョアンの歌とギターは微妙なピアニシモからフォルテシモまで柔軟に表現する。僕はジョアンのライヴCDを3種類持っているが、このダイナミクスはCDで再現しきれない。
ギターの響きもCDで聴くのとでは違う。コードそのものも若い頃の録音とは違うし、そもそもキーが低くなっている。人差し指、中指、薬指でコードを弾くボサノヴァ独特のギター奏法だ。CDよりも軽く、歯切れがいい。歌いながら複雑なシンコペーションを弾く。親指で正確に刻むツービートの低音はベーシストがいるような錯覚に陥るほどだ。一人でつとめているステージとは思えない。まさに伝説通りだ。
ギターばかりではなく、〈ワンノート・サンバ〉、〈シェガ・ヂ・サウダージ〉、〈コルコヴァド〉などボサノヴァのスタンダード曲も、CDで馴染んできた節回しとは違っていた。コードを研究するように、歌い方の研究もつづけているのかもしれない。
そんなことよりも、ジョアンの声だ。音程が狂っているようなボサノヴァの曲を、寸分違わぬ正確な音程で歌う。これも伝説通りだった。
〈ホーザ・モレナ〉、〈エスタテ〉、〈ワンノート・サンバ〉、アントニオ・カルロス・ジョビンの〈イパネマの娘〉や〈波〉、珍しい〈オール・オブ・ミー〉(もちろんポルトガル語版だ)など聴きたい曲を聴くことができた(全部で27曲!!)。ジョアンを生で聴くことなど夢のまた夢だっただけに、僕としてはもう思い残すことは何もないと言っても過言ではない。
ひとつだけジョアンらしい「奇行」を記しておこう。アンコールの拍手に応じてステージに再登場し、〈ア・フェリシダーヂ〉を歌った後、ジョアンは左手を左膝の上に、右手をギターの上に置いたまま動かなくなった。
客席からは盛んに拍手が送られている。
なおもジョアンは動かない。
15分が過ぎ、20分が過ぎたころ、ようやくステージマネージャーらしき男性が出てきた。ジョアンの肩にそっと手をやると、ジョアンが体を起こした。
どうやら寝てしまったようだ。5000人の鳴りやまない拍手のなか、ステージの上で。
だが、ジョアンは寝ていたわけではなかった。ステージの真下まで行って確かめたファンがいた。ジョアンは「起きていた」という。
ジョアンは何か呟き、「ありがとう、ジャポン」と両手を合わせた。よほど日本を気にいってくれたらしい。
それからのジョアンがまた凄かった。ノンストップでまた歌いつづけ、終わったのが10時45分。スタンディングオベーションに僕も加わり、豊穣で濃密な時間に別れを告げた。
ジョアン・ジルベルトはアントニオ・カルロス・ジョビンと並んで、ボサノヴァの創始者の一人だ(詩人のヴィニシウス・ヂ・モライスも忘れてはならない存在なのだが)。ボサノヴァの大きな特徴であるバチータというギター奏法はジョアンが発案したものだし、ぼさぼさと囁くように歌う(親父ギャグですみません)歌唱法もジョアンがはじめたものだ。
ところで、ジョアン・ジルベルトの名はモダンジャズのサックスプレイヤーだったスタン・ゲッツと共演した『ゲッツ/ジルベルト』というアルバムによって広まった。
グラミー賞を受賞したこのアルバムによってボサノヴァが東洋の島国まで知られるようになったのは喜ばしいことだけれど、結果的にこれが誤解を生んでしまった。つまり、ボサノヴァはジャズの1ジャンルだという誤解である。
ここでボサノヴァの歴史を語るスペースはないが、一般的にボサノヴァは「サンバをルーツに、ジャズの影響を受けて誕生した音楽」ということになっている。それを言うならドヴュッシーやヴィラ・ロボスといったクラシックの影響も受けているのだが。
アントニオ・カルロス・ジョビンは晩年に「ボサノヴァはジャズとは関係がない」と繰り返していた。
たとえば、ジャズミュージシャンはしばしば「ボサノヴァをやります」などと紹介して、ケニー・ドーハム(ジャズ・トランペッター)の〈ブルー・ボサ〉を演奏したりするが、これは「民謡をやります」といって三橋美智也の〈達者でナ〉とか美空ひばりの〈リンゴ追分〉をやるようなものです。これは音楽のジャンル分けの話ではなく、歴史と文化の視点の問題なんですね。〈達者でナ〉も〈リンゴ追分〉も確かに民謡風の曲ではあるけれど、これを民謡だという人は誰もいない。同じように〈ブルー・ボサ〉もボサノヴァ風ではあるけれど、ボサノヴァではない。
つまり、ボサノヴァがジャズから受けた影響よりも、ボサノヴァがジャズに与えた影響のほうが遥かに大きいことがこのことからもわかる。
しかし、まあ、とうのジョアン・ジルベルトにとって、こんなことは「どうでもいい」のだと思う。だって、ジョアンは常にサンバを歌っているんだと言ってるくらいで、ボサノヴァ歌手という認識はないらしい。
ジョアンをカエターノ・ヴェローゾ(ブラジル音楽界の左大臣みたいな人です。ちなみに右大臣はジョルジュ・ベンかジルベルト・ジルかな。あ、ジルベルト・ジルは本物の大臣になったんだ。文部大臣でしたね)は「ボサノヴァはジョアンそのものだ。しかし、ジョアンは遥かにボサノヴァ以上だ」と評した。その通りだと思う。
演奏曲目は以下の通り。
|