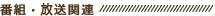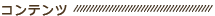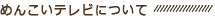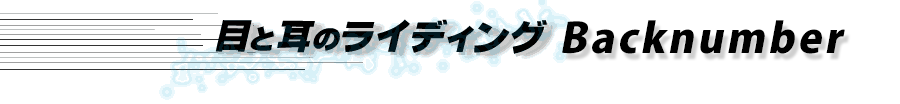
◆第295回 ナベサダとジャズ(13.May.2013)
| 4月20日、ジャズ喫茶一関ベイシーで渡辺貞夫を聴いた。メンバーは渡辺貞夫 (as)、小野塚晃 (p)、コモブチキイチロウ (b)、石川雅春 (ds)、ンジャセ・ニャン (per)のカルテット+パーカッション。 近年のベイシーでのナベサダさんのライヴは二夜連続公演だ。私が行ったのは二夜目だった。立錐の余地のない混みようで、私は2時間、立って聴いた。 エレクトリック楽器の入っていないアコースティック・カルテットということもあって、フュージョン系の曲でも本領発揮というべきか、チャーリー・パーカーをルーツとするビバップになるのが凄い。しかし、その年季の入ったフレージングもさることながら、包み込むようなサウンドを肌で感じて、「いったいこれは何なんだ?!」と総毛立った。 ボサノヴァを2曲「カーニバルの朝(黒いオルフェ)」と「シェガ・ジ・サウダージ(想いあふれて)」を演奏してくれたのも嬉しかった。なにしろナベサダさんは日本にボサノヴァを紹介した張本人だ。 ただし、アメリカ経由で入ったため、日本ではボサノヴァがジャズの1ジャンルと誤解されたまま定着してしまった。ボサノヴァはジャズの1ジャンルなどではなく、ブラジルのムーヴメント(音楽に限らず、電化製品やお菓子などにボサノヴァという語が使われるほど一世を風靡した)だった。もちろん、この誤解はナベサダさんのせいではないし、改めて言うまでもなく、ボサノヴァを積極的に日本に紹介した功績は計り知れないほど大きい。 |
|
ナベサダさんのライヴはいつも「ご機嫌」な気分にさせてくれる。この「ご機嫌」は死語となってしまったが、ナベサダさんやベイシーのマスターの菅原さんはごく自然に今も「ご機嫌だね」と口にする。私が言ってもサマにならないが、このお二人だといかにも「ご機嫌」な感じがする。 ナベサダさんの「ご機嫌」な音楽は誰にでもわかる。けれども、安易な音楽という意味ではない。うるさ方の「通」も満足する。こういうことは、めったにあるものではない。 |
|
私がナベサダを初めて意識して聴いたのは中学生のころだった。AMラジオで東京からの雑音交じりの番組をよく聴いていて、『ナベサダとジャズ』もそうやって聴いた番組のひとつだ。ジャズのことは何にも知らなかった。『ナベサダとジャズ』を聴くという行為がカッコいいことだと私は思っていた。何にもわからずに聴いていたが、結果的にそのおかげで耳が鍛えられた。 大学に進んでからは、FM東京の『渡辺貞夫マイディアライフ』を聴いた。これはカセットテープに同録(当時はエアチェックといった)し、山のように溜まったものだ。あれをとっておけばよかったと何度も後悔した。 そんなわけで、十代の私はナベサダさんのラジオ番組によってジャズを勉強した。そのナベサダさんが今なお最前線で元気に活躍されているのだから、ただただ頭が下がるばかりだ。 |
| 〈このごろの斎藤純〉 |
| 〇4月末に台湾へ行ってきた。「南の国は苦手」と私は思い込んできて、これまで何度かあった台湾行きの機会を敬遠してきたが、実際に行ってみて認識を改めた。台湾について勉強を始めたところだ。 |
| 『幻想の摩天楼』/スティーリー・ダンを聴きながら |
|

 ブログ:
ブログ: