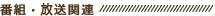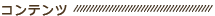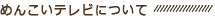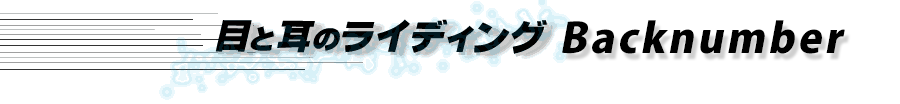
◆第303回 シューマン夫妻の音楽を聴く(9.Sep.2013)
| 8月31日(土)、私が芸術監督を仰せつかっている岩手町立石神の丘美術館ギャラリーホールにおいて、盛岡出身でオーストリア在住のクノップ(長岡)直子さん(ピアニスト)、その次女クノップ・アンナさん(ヴァイオリン)、盛岡市在住の三浦祥子さん(チェロ)による『室内楽の夕べ』が開かれた(美術館友の会主催)。 このコンサートで注目すべきことは何といっても直子さんとアンナさんの親子共演にあるが、プログラムもユニークだ。そのプログラムをご覧いただきたい。 |
|
【第1部】 |
| 一見しておわかりのとおり、ロベルト・シューマンとその妻のクララ・シューマンの作品で組んである。題して「シューマン夫妻の愛の調べ」。 クララが当時の人気ピアニストで、シューマン家の家計を支えていたことはよく知られている。が、作曲をしていたことを知っている人はずっと少なくなるだろう。 改めて考えてみると、クラシックの有名な女性作曲家っているだろうか。 大急ぎでお断りしておくと、作曲家に男性も女性も関係ない。もちろん、それはまったくそのとおりだ。しかし、それは現代の話であって、19世紀の社会ではそうではなかった。女性に作曲ができるはずがない、と信じられていたのだ。簡単な話、女性蔑視・女性差別があったため、どんなに優秀な作曲家であっても、女性というだけで認められることはなかった。そんな馬鹿なと思うが、そういう時代だったのだ。 もっとも、女性のほうもずっと差別されっぱなしだったから、クララほどの人でも自作に対して「力と、ところどころ発想にも欠けるのは、所詮、女の仕事」(当日のパンフレットから)という評価を下してしまっている。 |
| とはいえ、女性作曲家がまったくいなかったわけではない。モーツァルトの姉も作曲ができたし、メンデルスゾーンの姉ファニー・メンデルスゾーンも作曲家だった。ほかにもたくさんいると思うが、ごくごく一部の人にしか知られることがなかった。それほど音楽の世界は男性優位だった。 同様のことは指揮者についてもいえるし、ジャンルは異なるものの画家についてもいえる。 |
| このコンサートではロベルトとクララの作品が対等に扱われている。決してロベルトのおまけではない。こういう動きは欧米ではすでに見られていて、クララ・シューマンをはじめファニー・メンデルスゾーンら女性作曲家の再評価の気運が高まっている。日本では先駆的な取り組みといっていいと思う。 したがって、このコンサートで初めてクララの作品を聴き、その魅力を知った方も少なくないだろう。実は私自身、クララの作品を聴くのは初めてだった。そして、クララ・シューマンはこれからもっと聴いていきたい作曲家の一人となった。 |
| このプログラムとまったく同じ内容のコンサートが、前日にもりおか啄木・賢治青春館でおこなわれた。私はそれも聴いている。三浦祥子さんが、集中力の高い演奏でこれまでにない奥行きを感じさせたことが印象に残った。おそらく、これまで聴いてきた数々の演奏の中でベストの演奏だ。驚くことに、翌日はさらによかった。 三浦さんは、いわてフィルハーモニーオーケストラの第2回定期公演(バックナンバー第302回をご参照ください)を8月11日に終えたばかりだ。こういう大舞台の経験が如実にあらわれている。 |
| 前日にアップライト・ピアノとは思えないような演奏でもりおか啄木・賢治青春館の満員の聴衆から賞賛の拍手を浴びた長岡直子さんは、石神の丘美術館のグランドピアノで本領をいっそう発揮した。やはり、音圧の面でも細かいニュアンスの表現力の面でもグランドピアノに軍配が上がる。 アンナさんには前日のコンサートでの思いきりのいい演奏に大きな可能性を感じた。ときおり粗削りなところが気になったが、翌日のコンサートではそれがなくなっていた。アンナさんはミネッティ弦楽四重奏団のメンバーとしても活躍していて、本当にこれからがますます楽しみだ(よけいなお世話かもしれないが、本をたくさん読みなさいとアドバイスしようと思っていて、忘れていた)。 |
| 〈このごろの斎藤純〉 |
| 〇県央豪雨災害お見舞い申し上げます。私も一度だけ民家の泥出しのボランティアに参加してきましたが、その際、まだ手がつけられていない場所も目にし、被害の大きさに驚かされました。冬が来る前に完全に復興できることを祈っています。 |
| シュニトケ:ピアノ五重奏を聴きながら |
|

 ブログ:
ブログ: