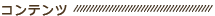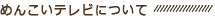◆第315回 英国美術の黄金時代 その1 (10.Mar.2014)
|
クラシック音楽や美術の分野において、イギリスは実に不思議な国だ。あれだけの歴史(と文化)を持ちながら、クラシック音楽においても美術においても世界の表舞台に出てくるのは19世紀になってからだ。 ひとつの大きな理由は島国だったからなのかもしれない。 私たちはヨーロッパというときにイギリスも含めてしまいがちだが、イギリスの人々はヨーロッパを「大陸」と分けてとらえている。通貨はいまだにポンドのままという徹底ぶりだ(同じ島国であるアイルランドはユーロを使っているが)。つまり、ヨーロッパでありながら、ヨーロッパではないというイギリスのあり方が、芸術分野でも独自のスタンスを保持することになったのではないだろうか。 もうひとつ、イギリスは古くから諸外国との交易が盛んだったから、優れた文化も他国からどんどん入ってきたため、自国で生む必要がなかったのかもしれない。事実、ヨーロッパ(大陸)とは一線を画していたにもかかわらず、決してその芸術文化が他国と比して劣っていたわけではない。ただ、フランスやイタリアの美術、ドイツの音楽のようには他国への影響を及ぼすものは生まれなかった。 そんなイギリスでも19世紀も半ばになると、まず美術の分野で黄金時代を迎え、少し遅れてクラシック音楽でも大輪の花が咲きはじめる。それも次から次へと咲いていく。 英国近代音楽の話は別の機会に譲るとして、イギリス美術黄金時代を扱ったふたつの展覧会が同時に開催されている。『テート美術館の至宝 ラファエル前派展 ヴィクトリア朝絵画の夢』展(森アーツセンターギャラリーにて4月6日まで)と『ザ・ビューティフル 英国の唯美主義主義1860-1900)』展(三菱一号美術館にて5月6日まで)がそれだ。 |
|
ヴィクトリア朝時代にイギリス美術がそれまでの眠りから醒めたかのように活況を呈した背景には、産業革命による市民階級の台頭(それに反比例するかのように教会と貴族階級は衰退していく)があった。 教会や貴族階級に好まれ、ある意味では保護もされていた当時の美術は、形式主義に凝り固まり、そのため停滞に陥っていた。若い芸術家たちは押しつけられる古臭いものに飽き飽きしていた。様式化される以前の(ラファエル以前の)芸術に立ち返ろうと集まったのがミレー、ハント、ロセッティら19歳から22歳という若い画家たちだった。彼らは「ラファエル前派兄弟団」と名乗った。 |
|
ラファエル前派兄弟団の設立趣旨を見ると、独創的であること、自然をよく観察すること、型にはまったものや古い習慣は拒否することなどが挙げられ、そして(ここが大切なのだが)美しいものを制作することと宣言している。 なんだか、あたりまえのことしか言っていないような気がする。が、あえてあたりまえのことを言わなければならないほど、当時のイギリスの美術界は停滞していたということがわかる。 ところが、(当然ながら、と言うべきか)彼らの作品は保守派から猛攻撃を受けた。たとえば、ブラウンは「ペテロの足を洗うキリスト」でキリストを描くときに、それまでの「決まりごと」にしたがわず、キリストを人間的に描いた。ラファエル前派兄弟団の画家が描く天使には羽が生えていなかったりした。これは教会から見れば許されないことだった。その「決まりごと」を教えることで権威を保ってきたロイヤル・アカデミーも、当然、批判の先頭に立った。 |
|
そんな彼らを擁護したのが、ジョン・ラスキンだった。美学者であり、美術評論家であり、画家でもあったラスキンの影響力は強かった(ラスキンはターナーをいち早く評価し、そのおかげでやがてターナーは英国を代表する画家となった。これはターナーにとってばかりでなく、結局のところ英国美術界にとって大きな幸福をもたらした)。 ラファエル前派兄弟団にとってラスキンは精神的支柱となった。イギリス芸術の未来を憂いていたラスキンにとっても、彼の思想を実現するラファエル前派兄弟団の登場は心強かったことだろう。 |
| 以下、第316回に続く。 |
| 〈このごろの斎藤純〉 |
| 〇今年は雪が少ないので、去年よりも早くロードバイクに乗れそうだ。そう思ってさっそく整備をしたら、とたんに冷え込みが厳しくなった。残念。 |
| 一ノ瀬トニカ:美しかったすべてを花びらに埋めつくして…を聴きながら |
|

 ブログ:
ブログ: