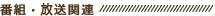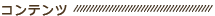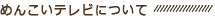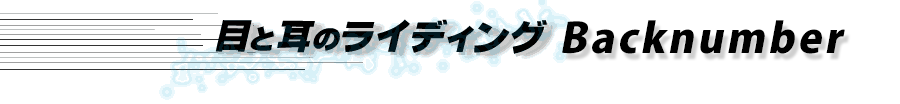
◆第325回 デュフィに惚れ直す (4.Aug.2014)
|
私が絵を観る喜びを知ったのは、デュフィとマティス、そしてピカソのおかげだ。そのデュフィの大きな展覧会があった(6月7日~7月27日、Bunkamura ザ・ミュージアム)。 結論から言うと、また惚れ直した。展覧会場から後ろ髪をひかれる思いで展覧会場を後にしたが、盛岡に帰ってきてからも毎日のように図録を開いている。こんなことは珍しい。 |
|
ところが、いざデュフィについて何か書こうとすると、手の動きも頭の回転もピタリと止まってしまう(もともと頭の回転はスローなのだが)。あれこれ考えながら何とか文章をまとめようとしても、言葉が指のあいだから漏れ落ちていく。そんな感じだ。 そこで、いつものように「なぜ、私はデュフィに惹かれるのか」をまず考えてみたい。 (1)既成の美術(あるいは美意識)を軽々と突き抜けて、独特の美術(あるいは美意識)をつくっている。 (2)上記と重なるが、自由を感じさせる。 (3)絵の題材からその色彩も含めて、あくまでもポジティヴな印象を与える。 (4)ノスタルジーを刺激する。 と書いてみたものの、ま、これだって後付けの理由だ。一目惚れに理由などないのは男女の出会いと同じ。 |
|
少し子細に検討していくと、たとえば・で私は「軽々と突き抜けて」と書いたが、今回の展覧会によってデュフィが実は努力の人だったことがわかった。決して天才のひらめきだけではないのだ。デュフィは、しかし、努力の痕跡を作品に見せない。これはデュフィを考えるうえで大切なポイントかもしれない。 (1)と(3)は色彩の明るさに加えて、描かれた題材からもそういう印象を受ける。たとえば、日本とは違って上流階級の社交場だった競馬場、クラシックのコンサートホールなど。 (4)については特に説明が必要だろう。私は小さいときから繁華街で育った。だから、小学校に上がる前からごくあたりまえのように喫茶店にも入っていた(もちろん親や、親の友人に連れられて)。1960年代の喫茶店(や飲食店)ではデュフィ的なもの(カレンダー、複製画、デュフィ風の絵)が今よりもたくさん見ることができた。これはマティスとピカソにも言える。だから、私はデュフィ(とマティスとピカソ)を見ると、ノスタルジックな気分になる。 今から27年前、私は初めてパリを訪れた。子どものころからフランス映画で見知っていた(私の生家は洋画専門の映画館だった)から、パリの街並みがとても懐かしく感じられた。そして、パリ市立美術館でデュフィ最大の作品(壁画)を初めとする多くの作品を見たときの感激といったらなかった。 デュフィ展の会場を歩きながら、そんなことを思いだしていた。デュフィは私にとってやはりノスタルジーを刺激する画家らしい。 それにしても、会場がとても混んでいて驚いた。最終日が迫っていたせいもあるだろうけれど、日本でデュフィがこんなに人気があるとは知らなかった。デュフィが好きなのは少数派だと思っていたから、己の不明を恥じるばかりだ。 |
| 〈このごろの斎藤純〉 |
|
〇サイクリングが楽しくてしようがない。盛岡近郊を自転車で走りまわってみると、実に美しいところだらけだと思う。 〇ツーリングも楽しくてしようがない。岩手県内をオートバイで走りまわってみると、日本で一番美しい土地に住んでいると実感する。 |
| フィンジ:エクローグを聴きながら |
|

 ブログ:
ブログ: