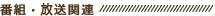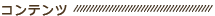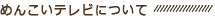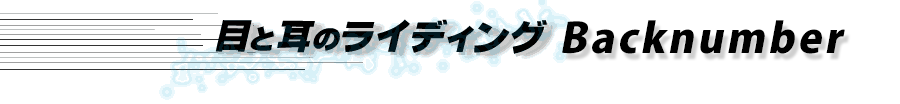
◆第341回 ポーランド音楽づいている今日このごろ (6.Apr.2015)
| 『岡崎ゆみ ピアノリサイタル2015』(虎ノ門JTホールにて4月2日午後7時から)を聴いてきた。オールショパン・プログラムだから、前回に続いてポーランドものについて書くことになる。意図したわけではなく、たまたまそうなったのだけれど、こういう偶然が私にはおもしろい。 |
|
岡崎さんはテレビでも活躍されているから、ご存じの方も多いと思う。この日も慣れたトークで曲を解説などをなさった。これがとても楽しく、一種のレクチャーコンサートの趣もあり、いろいろと勉強になった。もちろん、演奏がそのトーク以上に素晴らしいことは言うまでもない。 プログラムは次のとおり。 |
|
(1)華麗なる大円舞曲 第1番 作品18 (2)華麗なる円舞曲 第4番 作品34-3 (3)ワルツ 第6番 「小犬のワルツ」 作品64-1 (4)ワルツ 第8番 「別れのワルツ」 作品69-1 (5)練習曲 「牧童の笛」 作品25-1 (6)練習曲 「別れの曲」 作品10-4 (7)練習曲 「革命」 作品10-12 (8)マズルカ 作品24-1 (9)バラード 第1番 作品23 (10)ノクターン 第8番 作品27-2 (11)24のプレリュード 作品28より第15番 「雨だれ」 (12)ポロネーズ 「英雄」作品53 (13)スケルツォ 第2番 作品31 (アンコール)ノクターン 第5番 作品15-2 |
|
(1)から(4)は3拍子の曲、(8)と(12)はポーランドの3拍子(これについて岡崎さんはわかりやすく解説をしてくださった)。クラシックを聴いていて思うのは3拍子には哀愁を含んだ旋律が多いということ。ショパンの場合、それがさらに際立つ。(1)と(2)はウィーンでワルツを聴いて作曲したそうだが、ショパンはウィーンのワルツについて「音楽的にはたいしたことない」と感じたそうだ(これには私もまったく同感なのだが、恐れ多いので黙っていることにしよう)。 プログラムには載っていないが、(8)の後でサンサーンスのマズルカ第1番が演奏された。このとき、「どちらがショパンでどちらがサンサーンスが当ててください」と曲順をあえて紹介せず、聴き比べをした。 ショパンのマズルカはいかにもショパンらしい曲だったし、サンサーンスのマズルカはいかにもサンサーンスらしい(フランス音楽らしい)曲で、ピアノ音楽に疎い私でも間違いようがなかった。 |
|
標題の付いた作品もあるが、いずれもショパン自身が付けたものではない(だから、ショパンに「私はあなたの『別れの曲』が好きです」と言っても「そんな作品をつくった覚えはない」と言われるだけです)。ほとんどは後世の人による命名だが、「革命」は同時代のピアニストでショパンの友人でもあった(ライバルでもあった)のリストが付けた。ちなみに、(2)は「子猫のワルツ」と呼ばれることもある。 (9)はゲストにヴァイオリンを勉強中の石塚アレクサンダー・ホッブスとの共演でウジェーヌ・イザイによる編曲版が演奏された。イザイが好きな私もこのバージョンを聴くのは初めてだった。それもそのはず、2010年に楽譜が発見されたばかりだという。 ヴァイオリンの超絶技巧を要求する作品で、勉強中とはいえ石塚アレクサンダー・ホッブス(まだ青山学院高等部2年生だ)の高い技術力と音楽性が存分に発揮されていた。実に将来が楽しみだ。 内輪の打ち上げの席には岡崎さんと同じ事務所の麻倉未希さん、蜷川有紀さんもお見えになって、ユニークなスピーチをされた。それぞれジャンルは異なるが、この3者には「名前が2文字」という共通点があると言って岡崎さんが笑っていた。 また、このとき岡崎さんが「トークもちゃんと原稿を書いて、しっかり練習しています。ジョークもちゃんと練習して臨んでいるので、受けると嬉しいです」と裏話を披露なさった。これにはびっくりした。トークまで練習して本番に挑むという話はあまり聴いたことがない。根っからの努力家なのである。また、音楽も含め、コンサートをすみずみまで楽しんでいただこうという姿勢のあらわれだと思う。見習いたいものだ。 |
|
見習いたいといえば、岡崎さんはこの日のコンサートをひとつの節目にして、リサイタル活動をしばらく休まれるそうだ。音楽を勉強しなおすためだ。 音楽の研究が進み、岡崎さんが習ったショパンと現代のピアニストが弾くショパンは違うのだという。 常に挑戦をつづける岡崎ゆみさんの姿勢に敬服するばかりだ。復活リサイタルを今から期待したい。 |
| 〈このごろの斎藤純〉 |
| 〇例年より一ヶ月早くオートバイとロードバイクに乗りはじめた。が、例年よりも花粉が猛威をふるっていて、ツーリングやサイクリングの帰宅後は鼻水とくしゃみに悩まされている。 |
| トニー・ハッチ作品集を聴きながら |
|

 ブログ:
ブログ: