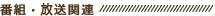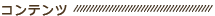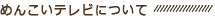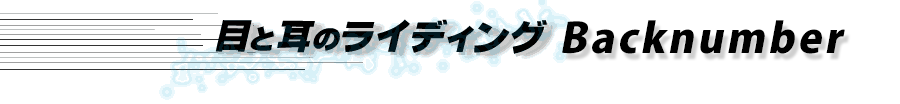
◆第358回 盛岡文士劇公演を終えて (21.Dec.2015)
| 第21回盛岡文士劇公演を無事に終えた。私が出演させていただいたのは時代物『源氏物語』である。紫式部による長大な王朝恋愛ロマンを、いつもの道又力さんが1時間15分ほどの芝居にまとめあげた。演出は昨年(第334回をご参照ください)につづいて、劇団わらび座の安達和平さん。ちなみに安達さんは、ご自身が主演をつとめる『政吉とフジタ』のロングラン上演と重なっていたため、かなりハードなスケジュールをこなすことになった。 |
| 道又脚本の特徴は、『源氏物語』と、それを書いた紫式部を描いた点にある。つまり、前者は「内」の世界で、後者は「外」の世界だ。私の役は「外」の世界に登場する藤原彰子(「しょうし」と読む)だ。つまり、女形である。私と同じ「外」の世界に登場する紫式部は内館牧子さん、清少納言は久美沙織さん(このコンビの掛け合いが絶妙で、演出家も舌を巻いていた)、そして藤原彰子の父親である藤原道長は井沢元彦さんがつとめた。 |
|
察しのいい方にはピンときたことと思うが、「外」の世界の配役は稽古にあまり参加できない作家が割り当てられている。「内」の世界はかなりの稽古を積む必要があるが、「外」の世界は本番のときに何かアクシデントが起きても大勢に影響がない。 つまり、道又脚本は稽古(準備段階)のことまで考えて書かれているわけで、これこそ職人芸と言っていいだろう。 |
| この脚本は安達さんの演出によって生命を与えられた。私たち出演者は安達さんの演出に絶対の信頼を寄せている。なにしろ、ひとつのセリフを3通りも5通りも言い分けてみせ、演技も自ら手本を示してくれる。それによって、私たち素人は導かれ、脚本に潜む新たな魅力が引き出される。「あの脚本がこんなふうになるのか」と出演者である我々は驚かされっぱなしだった。 |
| アンケートの結果を見ても、好評だった。努力が報われた。お客さまに喜んでもらえることが何よりなのだ。 |
| 盛岡文士劇は今回で21回を迎えた。このうち私は19本に参加している。私は舞台に向いていないと自覚しているので、当初はつらかった(傍からは「純さんはいつも楽しんでいる」と言われたものだが)。しかし、2011年の東日本大震災が私に変化を及ぼした。盛岡文士劇に参加できることに、1年ぶりにスタッフと再会できることに、満員の舞台に元気な体で立てることに、ただただ感謝の念を抱く。 |
| これを書いているのは公演のちょうど一週間後なのだが、まだ疲れが残っている。プロの役者さんはこういう生活を1年中(というよりも一生)つづけているわけで、我々凡人とは何もかも違う人種だと(もちろん、尊敬の意味を込めて)つくづく思う。 |
|
【キャスト】 紫式部(『源氏物語』の作者)=内館牧子(作家・脚本家) 藤原道長(紫式部に『源氏物語』執筆を依頼した公卿)=井沢元彦(作家) 明石入道(明石の君の父)=金田一秀穂(言語学者) 桐壺帝(帝。光源氏の父。桐壺の夫)=高橋克彦(作家) 清少納言(紫式部のライバル)=久美沙織(作家) 藤原彰子(道長の娘)=斎藤純(作家) 左大臣=北上秋彦(作家) 弘徽殿女御(皇妃)・桐壺の母=澤口たまみ(絵本作家) 安倍霊明(陰陽師)=谷藤裕明(盛岡市長) 光源氏(『源氏物語』の主役)=浅川貴道(読売新聞支局) 惟光(光源氏の家来)=菅原和彦(岩手日報) 右大臣(弘徽殿女御の夫)=菊地幸見(岩手放送・作家) 桐壺・藤壺・明石の君=米澤かおり(岩手めんこいテレビ) 六条後息所=下道愛莉(NHK盛岡放送局) 朧月夜=阿部沙織(エフエム岩手) 葵の上=中舘瑞希望(2015ミスさんさ) 良清(明石入道の家来)=松本伸(写真家) 忠良=道又力(脚本家) |
| 〈このごろの斎藤純〉 |
| ○盛岡文士劇を終え、これで私の2015年も終わった。後は静かに暮らすだけだ。さっそくスキーに行きたいところだが、あいにく暖冬の影響でスキー場のオープンが遅れている。 |
| スティーヴ・レイ・ヴォーン:グレーテストヒットを聴きながら |
|