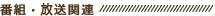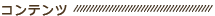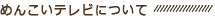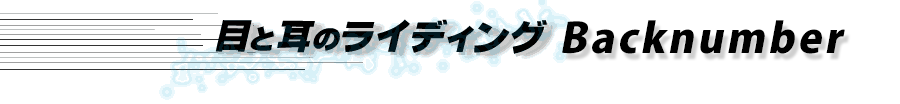
◆第359回 春画を観る (12.Jan.2016)
|
春画がブームだ。書店の美術書コーナーには春画に関する本がたくさん並んでいる。一般誌にも春画が堂々と掲載されている。 ところが、春画の実物にはなかなかお目にかかれない。この連載でも何度か書いているように、私たちが日本の文化である浮世絵(春画を含む)を観る機会は、印象派の絵画を観る機会よりも少ない。そういう歪(いびつ)な「文化」環境に私たちは生きている。 |
|
春画は改めて言うまでもなく、男女のセックスを描いた絵で、江戸期に人気の頂点を迎えた。枕絵や笑絵、ワ印など呼び方はいろいろあるが、現在は春画で統一されている。 エロティックアートはヨーロッパにもあったが、春画ほど高い芸術性を持つまでには至らなかった。それは、宗教の影響だと言われている。日本には太古の昔から、男根や女陰を「神様」として崇める風習があった。そういう「風土」が春画の底には流れいてると言っていい。 |
|
私が初めて本物の春画を観たのは、2013年秋、箱根に新しくオープンした岡田美術館の「18歳未満立入禁止」という一室でのことだ。それは写真よりもずっと鮮やかで、生々しかった。初めてセザンヌを観たときと同じくらい強いインパクトがあった。「ああ、これが春画というものなのか」と、ただただ溜め息をついたものだ。 次に観たのは、東京の礫川浮世絵美術館(浮世絵の研究家が小さなビルの小さな一室でコレクションを少しずつ公開していたが、2014年、惜しまれつつ廃館した)でだったが、このときは性器を隠していた。 そして、昨年、東京の永青文庫(旧熊本藩主細川家伝来の美術品、歴史資料や、16代当主細川護立の蒐集品などを収蔵し、展示、研究を行っている)で日本で(たぶん)初めての『春画展』が開催された。大英博物館が大規模な春画展を開いたときも驚いたが、元首相が春画展を開いたのだから、これにも驚いた(永青文庫の理事長は元首相の細川護煕氏)。 |
| 永青文庫の『春画展』の展示作品は100点を超えていた。岡田美術館や礫川浮世絵美術館での春画経験とは比べ物にならない。しかも、これまで本で目にしてきた有名作品もたくさん出ていた。細川家伝来のものもあったし、どこかのお武家さんから流出したらしいものものあった。やはり写真で観るのとは迫力が違う。驚きの連続だったが、何よりも驚いたのは来館者の客層である。圧倒的に女性が多く、しかも若い方も多かった。大英博物館の『春画展』も来館者の55.5パーセントが女性だったそうだが、永青文庫は女性の割合がもっと多かったに違いない。 |
|
春画は間違いなく日本の文化遺産のひとつだ。この文化遺産は明治維新後に否定され、ごく最近まで「恥ずべきもの」と思われてきた。昨今の変化には驚かされるばかりだ。
もっとも、「個人の楽しみ」である春画を、美術館という公の場で大勢で観ることへの違和感がないわけではない。これは、博物館に仏像が鎮座していることへ抱く違和感と、どこか似ている。 |
| 春画についてはまた機会を改めて書きたいと思うが、春画が「お守り」として扱われていたり、宮沢賢治が自身の春画コレクションを友人に見せていたということはメモ代わりに記しておきたい。 |
| 〈このごろの斎藤純〉 |
| ○明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。 ○昨シーズンから「雪も重要な地域資源だ。地域資源の有効活用をしよう」という思いから(それだけが理由ではないのですが)スキーを始めたのだが、記録的な暖冬のためスキー場が悲鳴をあげている。私も残念でならない。 |
| デレク&ザ・ドミノス:インコンサートを聴きながら |
|