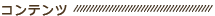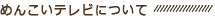◆第368回 待ち焦がれていたモランディを観る(30.May.2016)
|
岩手県立美術館で開催中(6月5日まで)の『モランディ 終わりなき変奏』展は私が心待ちにしていた展覧会だ。 なにしろ、名前はかなり知られているのに、国内の美術館でモランディを所蔵しているところがあまりないため、実際に観る機会がめったにない。 さらに、2011年に開催が予定されていた『モランディ展』が東日本大震災の影響で中止になり、幻の『モランディ展』と呼ばれることになった(あの年は東日本大震災と『モランディ展』の中止で二重のショックを受けた)。 それだけに待ちに待った展覧会となった今回の『モランディ 終わりなき変奏』は、中止になった『モランディ展』の作品構成を見直し、さらに充実させたものだという。 |
| ジョルジョ・モランディ(1890-1964)は生まれ故郷のボローニャを一生離れず、ほとんど同じモチーフを飽くことなく、描きつづけた。若いころから成功して収入にも恵まれたのに、お金にはまったく興味がなく、簡素な生活を守った。「守った」というのは比喩でも何でもなく、まさにその言葉通りで、煩わしい人間関係と距離を置き、絵を描くことだけに生涯を捧げた。 |
| モランディの生き方は作品にも如実にあらわれている。それは、壺、瓶、用途が不明ないろいろな置物をさまざまに配置した静物画である。2枚の絵や写真を並べて違いを指摘する「間違い探し」と、モランディの作品群は似ている。配置が少し違うだけで、ほとんど同じ絵柄の作品ばかりなのだ。この「さまざまな配置」を本展覧会では「変奏」と表現した。変奏は改めて言うまでもなく、ある主題を多様に形を変えていくという音楽用語だ(有名なものでは、モーツァルトの「キラキラ星変奏曲」がある。これはキラキラ星のシンプルな旋律がどんどん難しい曲に変化していく)。 |
| もうひとつの特徴はその渋く、くすんだ色調にある。モランディはテーブルに配置した壺や瓶などがその色調になるまで埃を被るのを気長に待って、それから制作を始めたそうだ。何とも気の長い話だが、モランディはある意味で「見たままの色」を描いたのだということもできる。 |
|
私が初めてモランディを知ったのは、いつだったろうか。たぶん10年くらい前に河出文庫の『須賀敦子全集』の一冊を手にとったときではなかったかと思う。装丁にモランディの作品が使われていた。私は静物画にはあまり興味を感じないのだが、モランディはなぜか気になった。 今回、初めて実物を目にして、その理由のひとつがわかったような気がしている。モランディの静物画は静物画ではない。いや、確かに静物画なのだが、ときとしてそれは建物に見えたり、人物の群像に見えたりする。もっと言うなら、抽象画に見えるものもある。モランディが抽象を意識していたかどうか、はっきりと断言はできないものの、水彩画作品では抽象化が明らかだ。これも今回の展覧会で発見したことだ。 |
| そんな発見を楽しみながら展覧会場を歩いていて、最後にはやはり結局のところ絵というものは画家の心象なのだというあたりまえの結論に行き当たった。 |
|
イタリアというと明るく陽気なイメージを我々は抱きがちだが、私が唯一訪れたことのある北イタリアのヴァッレ・ダオスタはそうではなかった。人々の話し声も身振りも決して大仰ではなく、見知らぬ日本人(私のことです)に話しかけられて、はにかむ姿が印象的だった。 モランディの故郷のボローニャは、私のような乗り物好きにとってはオートバイメーカーのドゥカティ、スポーツカーメーカーのランボールギーニとマセラティの本拠地があるところとして馴染みがある。また、問題作を撮りつづけた挙げ句、暴漢に刺殺された映画監督パゾリーニの故郷でもある。 ただ、こういう風土とモランディのつながりを見出すのは今の私には難しい(こういうとき、行けばわかることがしばしばある。行きたいなあ、ボローニャ)。 モランディはしばしば哲学的なイメージで語られる。私も柄にもなくモランディという哲学の森に迷いこんでいた。 |
| 〈このごろの斎藤純〉 |
| 〇5月21日に開催したザ・ジャドウズのライヴ(ライヴスペース・アルディラにて)は超満員の大盛況でした。記してお礼申し上げます。8月末に大きな舞台を控えているので、ますます精進する所存です。今後ともザ・ジャドウズをよろしくお願い申し上げます。 〇今月はこの連載の立案者だったKが亡くなって4年になる。今もときどき頭の中に生きている彼と「この映画は~」などと話し合うことがある。彼とは生前にカラヴァッジョの話で盛り上がったことがあった。生きていたらきっとモランディのことを延々と話し合ったに違いない。 |
| ウェザー・リポート:スポーティン・ライフを聴きながら |
|