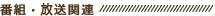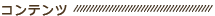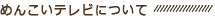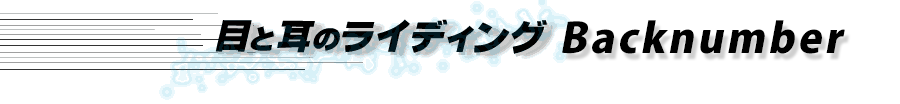
◆第377回 ピアノ四重奏の極致(11.Oct.2016)
|
クラシック音楽と一口に言っても、いろいろなジャンルがある。一般的に広く好まれているのはピアノ(ソロ)、次にオーケストラによる交響曲とオペラだろう。 私が最も好きなのは室内楽だ。 しばしば室内楽こそがクラシックの精髄だといわれる。さらには通好みともいわれる。私は必ずしもそうは思わない。交響曲よりも親しみやすく、名曲も多い。 小澤征爾は「オーケストラは室内楽が集まったもの」というようなことをおっしゃっている。その言葉を裏付けるように、オーケストラの指揮者である小澤征爾は室内楽のセミナーを日本と海外で主宰している。 オーケストラは指揮者の指示に従っていれば、音楽になる。一方、室内楽は指揮者がいないため、それぞれの演奏家に自主性が求められる。小澤征爾はその自主性をオーケストラの演奏者にも求めているといえる。 作曲家のフォーレは「室内楽こそが音楽の唯一の真の形式であり、個性のもっとも真正な表現なのです」という言葉を残している。そのフォーレの名を冠したフォーレ四重奏団のコンサートに行ってきた(9月30日、盛岡市民文化ホール大ホールで19時開演)。 |
|
フォーレ四重奏団は、1995年、ドイツ・カールスルーエ音楽大学卒のエリカ・ゲルトゼッツァー(ヴァイオリン)、サーシャ・フレンブリング(ヴィオラ)、コンスタンティン・ハイドリッヒ(チェロ)、ディルク・モメルツ(ピアノ)によって結成された。 室内楽グループは名演奏家がCD録音のために、あるいはコンサートツアーのために臨時に結成する場合が多い。そのほうがCDが売れる。ただし、コンサートツアーは名演奏家のスケジュール調整という高い壁があるためなかなか実現しない。 フォーレ四重奏団は固定したメンバーで20年も続いている。珍しいことだ。メンバーが固定しているから、それだけ楽曲に対して時間をかけて何度も取り組むことができる。それが演奏に深みを与える。 実際、その高い音楽性は、マルタ・アルゲリッチ音楽祭、シュレスヴィヒ=ホルシュタイン音楽祭、ラインガウ音楽祭、シュヴェツィンゲン音楽祭、ルートヴィヒスブルク音楽祭、メクレンブルク=フォアポンメルン音楽祭、キッシンゲンの夏音楽祭、オランジェリー・ドゥ・ソー音楽祭など世界中の音楽祭に引っ張りだこになっていることで証明されている。 |
|
今回のプログラムはブラームスのピアノ四重奏曲第1番ト短調作品25と、ムソグルスキーの「展覧会の絵」をフォーレ四重奏団自らが編曲したる「ピアノ四重奏版組曲『展覧会の絵』」と、どちらも実演に接する機会の少ない作品だった。ことに「ピアノ四重奏版組曲『展覧会の絵』」は予想を遥かに上回る傑作であり、ピアノ、ヴァイオン、ヴィオラ、チェロという編成のピアノ四重奏の可能性を最大限に発揮した名演だった。 「弦楽三重奏にピアノが加わっただけで、こんなに違うのか」と改めて感じた。ピアノという楽器はそれだけ音楽の幅を広げる力を持っている(だから、私はしばしば「ピアノはずるい」と言ったりする)。 この日は聴衆も素晴らしかった。ブラームスのピアノ四重奏を演奏中の聴衆の集中力はきっとフォーレ四重奏団にも伝わったに違いない。続く「展覧会の絵」でも聴衆の集中力は途切れず、それを感じとったフォーレ四重奏団も尋常ならざる演奏で応じた。 満員にはほど遠かったものの、幸運にも真にクラシックを愛する人たちが集まって、親密な空間をつくったともいえる。 それは、熱い聴衆の拍手に対してアンコールを2曲(フーベルトのフォーレタンゴ、シューマンのピアノ四重奏から第三楽章アンダンテ・カンタービレ)も演奏したことでもわかる。 このように、演奏家と聴衆が一つになって音楽をつくりあげることが室内楽の醍醐味でもある。主催者の立場からすれば、集客の難しい室内楽コンサートはリスクを伴うだろうけれども、クラシックファンを育てるという意味でも、今後も室内楽のコンサートに力を入れていただきたいと切に願う。 |
| 〈このごろの斎藤純〉 |
| ○盛岡文士劇の稽古がはじまった。演目は『みちのく平泉~秀衡と義経~』で、私は弁慶を演じます。弁慶役は二度目ですが、相変わらず貫祿のない弁慶なので何だか申し訳ないです。 ○10月15日の「中津川べりフォークジャンボリー」(プラザおでって)に出演しますので、ぜひお越しください。私の出番は夕方5時30分からで(コンサートは10時~21時)、懐かしい歌謡曲とフォークソングの名曲をお送りします。 |
| bohemianvoodooを聴きながら |
|