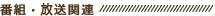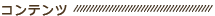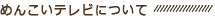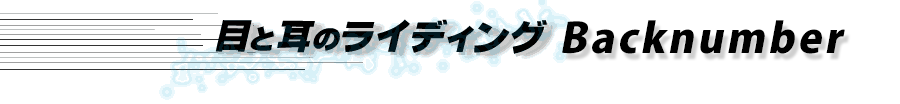
◆第395回 息の合ったヴァイオリンとチェロの二重奏(10.Jul.2017)
|
宮古市出身で現在はBBCスコットランド交響楽団のコンサートミストレス(コンサートマスター)をつとめている伊藤奏子さんが、夫でやはりBBCスコットランド交響楽団首席チェロ奏者をつとめているマーティン・ストーリーさんと二重奏のコンサートを、もりおか啄木・賢治青春館で開いた(7月8日午後6時30分開演)。 奏子さんのコンサートのようすについては、この連載でもたびたび取り上げてきたが、改めて振り返ってみると演奏を聴くのは3年ぶりかもしれない。 プログラムは下記のとおり。 |
|
第1部 〈1〉タルティーニ:ヴァイオリンとチェロのためのピッコロソナタ 〈2〉イベール:ギーラザナ(チェロ独奏) 〈3〉バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第3番ホ短調(ヴァイオリン独奏) 第2部 〈4〉バッハ:無伴奏チェロ組曲第1番ト短調(チェロ独奏) 〈5〉ピアソラ:タンゴ・エチュード(ヴァイオリン独奏) 〈6〉ヘンデル/ハルヴァーセン:パッサカリア 〈アンコール〉バッハ:G線上のアリア |
|
〈1〉は初めて知った作品だ。奏子さんもこのコンサートのために楽譜を探していて、図書館で「発見」したのだという。親しみやすい旋律ながら重音が多く、タルティーニらしい技法(ヴァイオリンにとっては演奏が大変だということ)もあちこちで聴かれた。一方、チェロは単純な通奏低音なので、マーティンさんにとってはあまり出番のない曲ということでもあった。 しかし、その分、〈2〉でマーティンさんの高い音楽性が発揮された。クーセヴィツキー(指揮者)の妻の死に捧げたというこの曲も初めて聴いた。『寄港地』と同じ作曲家とは思えないような複雑な音運びと調性(無調に聞こえないこともない)の作品だった。暗いといえば暗いのだが、悲しみというよりも瞑想あるいは哲学が連想された。 〈3〉について奏子さんは「演奏するたびに新しい発見がある」とおっしゃっていた。すっきりとまとまっていて、その明晰さは見栄ややハッタリとは無縁の奏子さんらしい演奏だと思った。 〈4〉はチェロ独奏曲の定番中の定番といっていい名曲だ。逆に演奏家にとっては、実にやりにくい作品でもある。マーティンさんの演奏は小さな川の流れが紆余曲折を経て大河になっていくさまを思わせた(こういう文学的な解釈は邪道であることは承知の上で、私の癖なのでお許しいただきたい)。 〈5〉この作品はフルート独奏のためのものと記憶している。ピアソラと奏子さんの組み合わせは意外だったが、「BBCスコットランド交響楽団で、聴いたこともないような曲をやった後などはクラシックを離れて別の音楽を聴いたり演奏したりしたくなる」そうで、ピアソラもお気に入りなのだという。 〈6〉はチェロとヴァイオリンのそれぞれの楽器のヴィルトゥオージティが要求される二重奏曲の傑作。もう何度もこの作品を演奏しているというお二人だけあって、息の合った名演を聴くことができた(実はけっこうスリリングな作品でもある)。馴染みの深い曲でアンコールの拍手に応えて、この日のコンサートは終わった。 |
|
終演後、久々にお二人にお目にかかった。コダーイにヴァイオリンとチェロの二重奏曲があると持ちかけると、やはり何度か演奏しているという。次回はぜひ聴かせてくださいと約束をして楽屋を後にした。
|
| 〈このごろの斎藤純〉 |
| 〇相変わらず公私ともに多忙な日常を過ごしている。が、活動した翌日は疲れきってグッタリしてしまう。こういうときに自分の年齢を感じる。 ○60代半ばの先輩(ともに現役で働かれていた)が相次いで他界した。寂しく、残念なことである。それにしても、今年は喪服を着ない月がない。 |
| サンタナ:天の守護神を聴きながら |
|