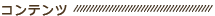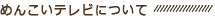◆第398回 文豪川端康成の審美眼(21.Aug.2017)
|
岩手県立美術館で開催中だった『巨匠が愛した美の世界 川端康成・東山魁夷コレクション展』が終わった(7月1日~8月20日)。とても好評だったようで、しばしば「行きましたか?おもしろかったですよ」などと声をかけられた。めったにあることではない。 やはり、知らない人がいない川端康成の名を冠している効果は大きい。足を運んでみると、そのコレクションの質と量に圧倒される。実に見応えがあった。 |
|
川端康成は美術好きで知られ、美術に関する随筆もたくさん残している。もちろん、私もそれを読んではいたが、実際に川端が眺めていただろう作品群を展覧会場で目にすると、興奮のせいなのか感激のせいなのか頭がくらくらしてしまった。 川端は目が肥えていた。好きで、よく絵を観ていたからだろう。もしかすると、それは夏目漱石の影響かもしれない(その夏目漱石の書も川端は所有していて、今回、初公開されている)。いわゆる書画骨董が多いものの、ピカソや古賀春江などモダン(前衛といってもいい)なものも理解していて、懐の深さを感じさせた。 川端のところにはまた名品が全国から集まった。美術好きが広く知られるようになって、骨董商・美術商が「先生、こんなのはどうでしょうか」などと持ち寄っていたからだ。そういう意味では川端は自ら探して歩く必要はなく、「いいもの」のほうからやってきた。その中には後に国宝に指定されるようなものもあった。いいものばかり見るわけだから、目が肥える。また、川端ほどの有名人を贋作で騙そうという無謀な輩もいなかったようで、そういう話は知らない。もちろん、こういう話は表になかなか出てこないものだが。 |
|
私がデビューした1988年当時は、川端を担当したことのある編集者がまだ現役で働いていた。数人の古参編集者から、川端が自殺したときの隠れたエピソードをうかがったことがある。 川端の自殺が報じられると、全国から骨董商・美術商が川端邸に押し寄せた。「これはまだお代をいただいていませんので持ち帰らせていただきます」と持ち去ろうとするのを、編集者たちは阻止すべく一致団結して見張り役についたという。 ちょっと補っておくと、骨董などの世界では「お代は後でかまいませんから、手許に置いてみてください」という商慣行があるそうだ。そばに置いて毎日眺めていると、手放したくなくなるのが美術好きというものだ(別の言い方をするなら、「これは置いておけんな。返そう」と思わせるようなシロモノは大したものではないということになる)。そういう美術好きの「性」につけこんだ商売と言えないでもない。 骨董商・美術商が持ち帰ろうとした品が、本当に未払いなのか支払い済みなのか、すぐには確認のしようがない。そこで「落ち着くまで今日のところは」とお帰りいただいたそうだ。本展に並んだ逸品は、そんな編集者たちの活躍によって守られた品々でもあったわけだ。 |
|
本展では川端と親交のあった東山魁偉のコレクションも同時に展示されていた。何か付け足しという感が拭えなかったが、これはこれで見応えがあった。
|
|
また、『伊豆の踊り子』を生み出すきっかけとなった初恋と破局について、二人の手紙が展示されている。東京帝大時代の川端が恋した伊藤初代の父は、岩手県は岩谷堂(現在の奥州市)の人だった。川端はその父に初代との結婚を認めてもらうために岩手を訪れている。 そのころ、川端の世話を一所懸命に焼いたのが、親友の鈴木彦次郎だった。彦次郎の名がちょくちょく出てくる川端の手帳を私はどこかで目にしているのだが、いつどこで見たのか思いだせない。 彦次郎は後に盛岡に疎開し、岩手県立図書館の館長をつとめるなどして盛岡で没している。『北の文学』(岩手日報社)、盛岡文士劇、私が編集長をつとめている月刊『街もりおか』(杜の都社)はいずれも彦次郎が始めたもので今も存続している。「もりおかふるさと会」会長の鈴木文彦さん(元文藝春秋社)は彦次郎のご子息である。 せっかく岩手で開催するのだから、川端と彦次郎の友情を示す資料も展示してほしかったと思うのは、ないものねだりだろうか。 |
| 〈このごろの斎藤純〉 |
| 〇さんさ踊りパレードが無事、成功裏に終わったとたんに盛岡は涼しくなり、秋の気配になった。暑くなるのが早かったが、涼しくなるのも早かった。 〇今週、私はオートバイ雑誌の取材で箱根界隈をツーリングしている。これが終わると私の夏も終わる。 |
| フィリップ・グラス:弦楽四重奏第一番を聴きながら |
|