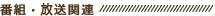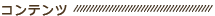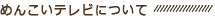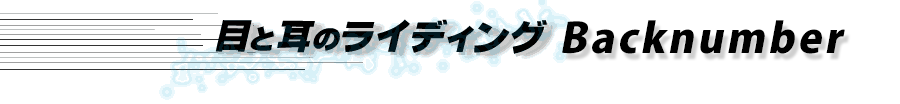
◆第363回 ドイツ・レクイエムを聴く その2 (8.Mar.2016)
|
第361回でお知らせした『ドイツ・レクイエム』のコンサート(盛岡市民文化ホール大ホール、2016年3月6日午後3時開演)は本当に素晴らしかった。結論をまず書いておくと、このコンサートで私はレクイエム(『ドイツ・レクイエム』だけに限らない)の神髄に触れたように思う。 まず、指揮者のハンスイェルク・シェレンベルガー氏のメッセージを紹介したい。 |
|
〈5年前、東日本を襲った巨大な地震と津波は壊滅的な被害を与え、多くの人々の命を奪いました。世界中を駆け巡ったその恐ろしい光景を、我々は決して忘れることはありません。 |
|
ほとんど付け加えることはない。このメッセージにあるままの音楽体験を、あの場所にいたすべての人がしたことだろう。 ブラームスの『ドイツ・レクイエム』は葬送の音楽ではない。もちろん、葬送の意味もあるが、むしろ生きている(生き残っていると言い換えてもいい)私たちの未来のための音楽であることを、シェレンベルガーは伝えようとしたのではないだろうか。実際、コンサート会場を後にする私の体の内には、慰めとと同時に生きる希望、あるいは勇気のようなものが満ちていた。 震災5年の節目にこのコンサートを聴けたことは私にとって大きな意味があった。おそらく、これは私だけの感想ではないと思う。 たまたま私の隣の席が盛岡大学の剣持清之教授(チェンバロ奏者)だった。終演後に感想を伺うと、響きの渋さに感銘を受けたとおっしゃっていた。確かに抑制の効いた演奏だった。そして、すみずみにまで神経が行き届いていた。オーケストラと合唱団を合わせて200名を超す大所帯であるにもかかわらず、とても繊細な音楽を実現していた。シェレンベルガー氏の要求に応えた盛岡バッハ・カンタータ・フェラインをはじめとする合唱団のみなさんに心から拍手を送りたい。ソリストの秦茂子さん(ソプラノ)、ドミニク・ヴェルナー(バス)も抑制の効いた渋い歌声を聴かせ、強い牽引力でリードした。 また、やはり大編成のフルオーケストラながら、ときに室内楽を想わせる響きも聴かせる岡山フィルハーモニック管弦楽団の底力にも、正直、驚いた。 この作品はブラームスのバッハやヘンデルへの尊敬を感じさせる古典的なスタイルでありながら、やはり随所にブラームスらしい「新しい響き」も散りばめられている。その対比がクリアに表現されていた。何度もCDで聴いている作品なのに、初めて聴いたような新鮮さを覚えた。いわずもがなのことだが、やはり音楽はCDでは本当のところはわからない。 |
| 〈このごろの斎藤純〉 |
| ○今シーズンは残念ながらスキーを楽しむには条件がよくなかったが、それでも少しは上達したのではないかと思っている。 ○春の訪れは嬉しいものの、花粉症シーズンの到来でもあり、いささか憂鬱でもある。昨秋から舌下免疫療法を始めたが、この効果が出るのは早くても来シーズンからなのだそうで、今シーズンはまだアレグラなどの薬のお世話になりそうだ |
| 中重雄:ミッションワンを聴きながら |
|