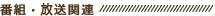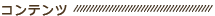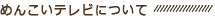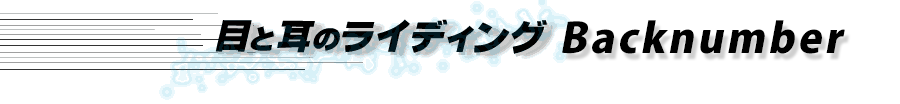
◆第390回 北東北のモダニズム(24.Apr.2017)
|
2009年の春(4月25日―7月5日)、岩手町立石神の丘美術館で私の芸術監督就任記念として『印象・岩手』展を開催させていただいた。このとき、展示作品のセレクションを一任されたことは私にとって至福の経験だった。なにしろ、私の「好み」で選んだ絵を、萬鉄五郎記念美術館や盛岡市から借りてきて集めたのだ。まるで夢のような仕事だったと言っていい。 石川酉三、板垣崇志、重石晃子、杉本みゆき、高橋和、長谷川誠、畠山孝一というラインアップになった。具象画と抽象画がほぼ半分ずつである。必ずしも「岩手の風景画」というわけではなく、「岩手の風土を感じさせる絵」をセレクトした結果だった。 おもしろいことがあった。「岩手の風土を感じさせる絵」として選んだ抽象画が実はヨーロッパ滞在中に制作された絵だったり、フランスの風景だと思って観ていた絵が実は岩手県南の風景だったり…。 |
||||||||||||||
|
このとき、重石晃子さんの作品を展示できたのは本当に光栄なことだった。重石さんの作品は私に「北東北のモダニズム」という問題意識を芽生えさせたきっかけになっている。 北東北のモダニズム」の意味をざっくりと大雑把に言うなら、東北は遅れた土地というイメージで語られがちだが(実際に経済の面ではそうだったかもしれないものの)、芸術文化に関しては明治以降、北東北出身者たちが近代化を牽引してきたのではないか…という問題提起である。 重石さんは1934(昭和9)年生まれだから、第389回で紹介した村上善男の1歳下だ。村上善男が抽象的な前衛芸術で「北東北のモダニズム」を表現していたのに対して、重石さんは風景画という違いはあるが、根っこのところでは重なっていると私は考えている。 |
||||||||||||||
| 重なっているといえば、お二人の共通点として、佇まいというか存在そのものが美しい。凛として颯爽、重厚にして軽やかでもある。作風は異なるものの、半世紀以上に渡って「北東北のモダニズム」を牽引なさってきた実績が、その美しい佇まいの底にある。 | ||||||||||||||
| このように言葉を並べるよりも、その作品を実際にご覧いただくほうがよほどわかりやすいだろう。岩手町立石神の丘美術館では4月22日から『風を追いかけて 重石晃子展』を開催中だ。百聞は一見にしかず。ぜひ足をお運びください。 | ||||||||||||||
| 【岩手町立石神の丘美術館からのお知らせ】 | ||||||||||||||
|
岩手にゆかりある近現代美術家を個展形式で紹介する〈北の作家シリーズ〉の一環として、盛岡市在住の画家・重石晃子の作品を紹介します。 1934年、盛岡市に生まれた重石晃子は、中学生のときに深沢省三・紅子夫妻に師事し、画家への道を歩みはじめます。 1952年、第1回生として岩手県立盛岡第二高等学校を卒業。その後、岩手県立盛岡短期大学美術工芸科に学び、1975年~1978年、トゥール美術大学(フランス)に留学。フランス美術家協会ル・サロン展、女流画家協会展、一水会展に出品し数々の受賞を重ねてきました。 また、東京純心女子短期大学美術科で教授として後進の指導にあたり、退職後は盛岡に戻り、深沢紅子野の花美術館館長を務めました。 この展覧会では、1970年代からの油彩風景画と共に画家の言葉を展示し、その画業をたどります。 ぜひこの機会にご覧いただければ幸いです。 『風を追いかけて― 重石 晃子 展』
|
||||||||||||||
| 〈このごろの斎藤純〉 | ||||||||||||||
| 〇愛車ホンダCB1100EX(愛称白馬号)で今シーズン最初のロングツーリングに行ってきた。残雪が鮮やかな奥羽山脈沿いに南下すると、盛岡ではまだ桜は蕾だったが、岩手県南と宮城県は花盛りだった。 | ||||||||||||||
| ボード・ブギー(サーフィンサウンドのオムニバスCD)を聴きながら | ||||||||||||||
|